
ビーシュリンプを飼育している多くの方が一度は経験している「大量死」。
僕も過去に色んな失敗をしてきましたし、これからもたくさん失敗すると思います。
相手は生き物ですから、いつかは死んでしまうものですが、あまりに頻繁に死なれてしまっては精神的にもお財布にも厳しいですよね。
大量死を経験すると、多くの人がビーシュリンプの死因について考えると思うのですが、その選択は間違っていないですし、改善できることがあるならすぐに行動した方が後の結果が良好なことが多いのも事実です。
昔からビーシュリンプの死因について多くの方が発信していますが、中には病死という意見もちらほら見受けられます。
ビーシュリンプの病気なんてあまり聞きませんが、ビーシュリンプが病気になることはあるのか、個人の憶測の範囲で書いてみようと思います。
エビの病気
エビが病気になんてなるの?って思う方もいると思います。
養殖エビの話になりますが、過去には東南アジアや沖縄で養殖のバナメイエビが感染性の病気により大量死したという事件は実際にあります。
エビの病気について知られているのは
- ホワイトスポット病ウイルス
- 急性肝膵臓壊死症候群
- 微胞子虫寄生虫
- モノドン型バキュロウイルス
- 感染性筋壊死ウイルス
- イエローヘッド病ウイルス
など様々な病名がありますが、いずれも海水及び汽水域に生息する食用の養殖エビの病気で、飲食関係の仕事をしていた時はエビの高騰で頭を抱えたものでした。
ビーシュリンプへの感染はあるのか?
現時点では研究課題にもなっていませんし費用対効果の面で今後も研究対象にはならないと思います。
上記の病気がビーシュリンプにも感染するのかどうかはわかりませんが、可能性はゼロではないと思います。
その他、エロモナス症やカラムナリス菌などの細菌による魚の病気がエビにも感染する可能性もゼロではないと思います。
自分の水槽で起こった大量死は病気によるもの?
YESかNOかで答えると「NO」です。
ただし、何カ月も世話もせず放置してて数が減る度にエビを買い足したり、湧き水などの天然水や拾った石、流木などを殺菌せずに使用している場合は水槽内に細菌を持ち込む可能性はあると思いますが、一般的な水道水を使用した飼育下で病気を持ち込み尚且つ発症させる可能性は限りなくゼロに近いでしょう。
ビーシュリンプの死因は環境によるものが大半
ビーシュリンプは熱帯魚や金魚に比べて難しい部類に入ると思いますし、一般的なアクアリウムの知識だけでは失敗することもあると思います。
アクアリウムの歴史上においてビーシュリンプ飼育というジャンルは始まったばかりといっても過言ではないですし、まだ知られていないこともたくさんあって、時には常識が通用しないこともあります。
時間のかけ方や工程においての違いはあれどしっかり水を作るという部分では共通するところではあります。
多くの人がいうビーシュリンプは水質の変化に弱いというのは間違ってはいないですが、厳密にいえば水質への適応能力は魚よりも広く、適正値はあるものの、あらゆる水質に適応できる生き物ですから、変化に弱いというよりも悪化に弱いと捉えるのが正解です。
よって、失敗する多くの人が水槽内の環境(水質)が悪いことを見抜けず、エビを入れたら死んでしまったということになります。
原因を探るのは大体上からの順になると思います。
- 環境の変化に耐えられなかった
- 水合わせの失敗
- 輸送のダメージ
- 血統の問題
- 個体の奇形や病気
実際のところ、熟練のブリーダーの方は上記について何の問題とも捉えていません。

環境の変化
しっかりと管理飼育している方は、ビーシュリンプがある程度の環境の変化に耐えられることを知っています。
水合わせの失敗
水質さえしっかりしていれば、水合わせが特別な意味を持つことではないので、新規に立ち上げた水槽やよそからの新規導入個体以外は、水合わせもせずに水槽間を移動させている場合も多いです。(水質変化に関してはヤマトヌマエビの方が弱いです)

輸送のダメージや血統の問題
輸送のダメージや血統の問題は、オークションやネット通販の出品者の力量によるものなので、そこから買うのをやめれば解決しますが、上の1と2を理解していないと結局どこから買っても同じ結果になりますし、水合わせに何時間もかけたりとますます原因究明が困難になります。

最終的に上記の問題をクリアしたと仮定して初めて病気を疑うことになると思いますが、一つ一つしっかり解決していけば最後の病気という疑いは限りなくゼロに近い数字となります。
まとめ
ショップさんや個人でも水槽を何本も所有している人からビーシュリンプが病気になって全滅した話は聞いたことがありませんし、もし病気になったとしたらたちまち全部の水槽に蔓延してしまうのですぐにわかります。
そしてビーシュリンプは魚と違って先祖は虫なので、寄生虫や薬害などで死亡することはあっても病気にかかって死亡するケースはほとんどないと考えるのが正解です。
仮に病気に罹ったと想定して魚病薬を使用して回復した実績があればどうしても病気を疑ってしまうことも多くなると思いますが、そもそも病気になるような環境下での飼育自体に問題があるので、しっかりと水槽を立ち上げて適切な環境で飼育してあげたいものですね。

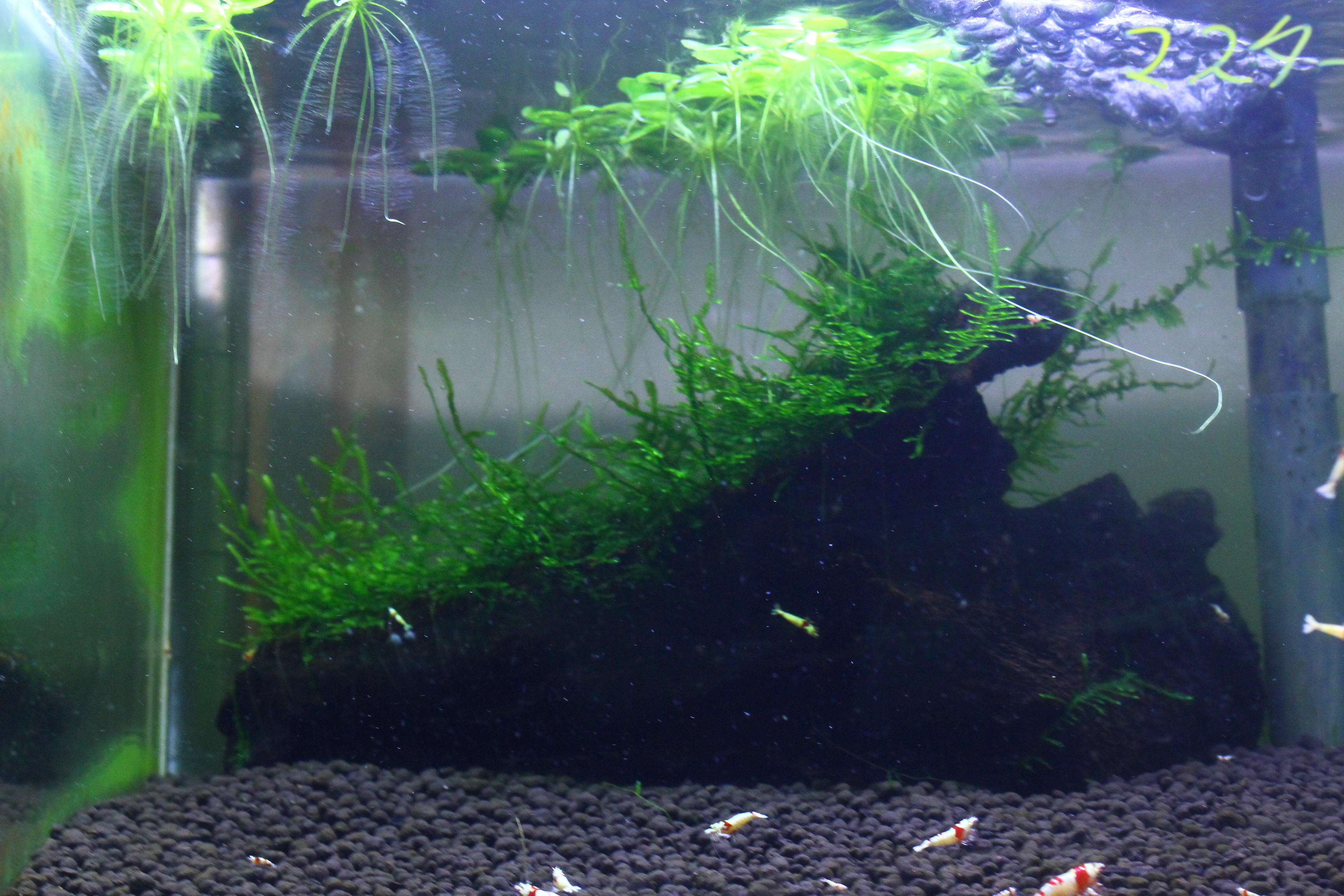






コメント